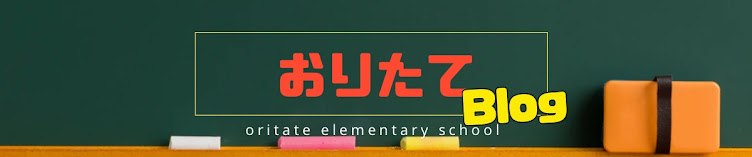1月27日(月)から2月7日(金)まで、体育委員会の企画で「長縄大会」が行われていました。
1~6年生の各クラスで、長縄を「8の字」で跳び、3分間跳んだ数を合わせて数えていきます。
高学年が有利かと思いましたが、体育委員がハンデを考えていました。
1・2年生は跳んだ数×3ポイント。
3・4年生は跳んだ数×2ポイント。
5・6年生は跳んだ数がそのままポイントになる。というルールです。
今日の昼の放送で、その表彰式の様子を動画で見ることができました。
1位は2年1組です。
143回も跳びました。×3で、429ポイントでした。大記録です!
2位は1年1組です。
81回跳んで、×3の243ポイントでした。がんばりましたね!
3位は3年2組でした。
最後に、「記録が伸びたで賞」の表彰です。
最初に跳んだ数から、最終日までにどれだけ伸びたのかという表彰も考えてくれました。
5年2組は100回以上も記録を伸ばしました。すごい!
回数で一番跳んだのは6年2組で180回でした。この回数はほとんどミスなく跳んでいた回数ですね!
最後に、体育委員長が「長縄大会の目的は、体力づくりとクラスの絆を深めることでした。」と伝えてくれました。
どのクラスも、縄に引っかかっても、すぐに切り替えて次のジャンプに集中していましたね。
体育委員さん、イベントは大成功でしたよ!